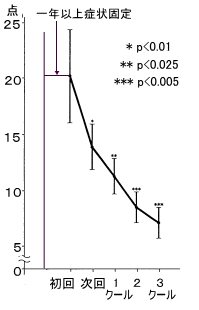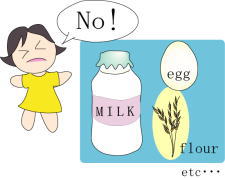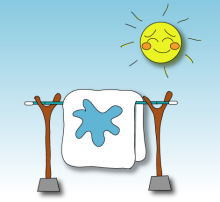気管支(小児)喘息とは?
わが国には百万人以上の患者がいるといわれています。
わが国には100万人以上の患者がいると推定されています。
半数は、10歳以下で発病し、このうちの3分の2は3歳以下、大部分は6歳までに発病しています。男児が多く、女児の2倍です。
このような子どもの気管支喘息を小児喘息といいますが、小学校高学年から中学入学ぐらいまでにかなりの患者は発作がおこらなくなり、成人になるまでには約半数が発作が起こらなくなります。
成人になってから発病することもあり、成人での男女比はほぼ同じになります。これは、結婚、妊娠、出産をきっかけとして発病する女性が増えてくるからです。
 喘鳴と呼吸困難を繰り返します。
喘鳴と呼吸困難を繰り返します。
喘息とは、喘(あえ)ぎ、苦しみながら息をする、という意味で、呼吸のたびにひゅーひゅー、ぜいぜいという音をたて、呼吸が苦しくなって、努力をしなければ息を吸ったり吐いたりできない状態を表した言葉です。
気管支喘息は、この喘鳴と呼吸困難が急に起こり、何時間か続いた後おさまってしまうことを繰り返す病気です。
喘息発作は、たいてい夜間におこり、明け方になるとおさまってきます。このようなことがある日数続いた後、発作が起こらなくなって、しばらく期間を経たあとにまた再発してきたりします。
喘鳴発作は気管支内腔が狭くなって起こります。
気管支喘息の患者の気管支は過敏で、健康な人ではなんでもないような刺激が加わっても、過激な反応を起こしてきます。
気管支に刺激が加わると、①気管支を取り巻いている平滑筋が痙攣を起こして気管支が収縮する、②気管支の粘膜がむくんでくる、③気管支粘膜の分泌腺から粘りけの強い粘液が多量に分泌されてくる、といった変化が広い範囲の気管支におこって、内腔が狭くなってきます。
その結果、気管支内の空気の通りが悪くなって呼吸困難におちいり、狭い気管支内を空気が出入りするさいの空気の流れの乱れから喘鳴が起こってくるのです。
喘鳴発作には誘因と原因があります。
気管支喘息の患者の気管支は過敏になっていて、刺激が加わると喘息発作が起こってきます。
発作を誘発する刺激には、ほこりや花粉の吸入、かぜや気管支炎などの呼吸器感染症、急激な気象や気温の変化、大気汚染、激しい運動、精神的ストレスその他さまざまなものがあります。
これらの刺激のうちのどれかが加わったときに喘息発作がおこる人もいるので、その刺激こそが気管支喘息の原因と考えられるケースもあるのですが、原因は別にあって、これらの刺激は発作をおこすきっかけ、つまり誘因としてはたらいている場合が多いのです。
気管支喘息の本質的な原因、いいかえれば、気管支を過敏にしている原因としては、従来からいろいろな説が提唱されてきています。
アレルギー説、自律神経失調症説、内分泌(ホルモン)調節異常説がそのおもなものです。
東洋医学研究所®グループの井島鍼灸院(岐阜市)では、気管支喘息に対して体質の改善と症状の緩和を目的とした鍼治療をさせて頂いております。
また、鍼治療によりストレスによる影響を軽減し、さらに、適切な生活指導をさせて頂くことにより症状の悪化を防ぐことができると考えます。
是非、副作用のない鍼治療を受けられることをお勧め致します。
 症状
症状



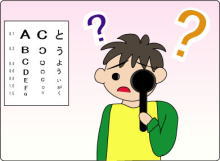

 鍼灸院に来院される患者さんの中で、耳鳴りを主訴として来院される方は少ないのですが、健康チェック表をつけて頂くと、多くの方が耳鳴りを感じておられることがわかります。
鍼灸院に来院される患者さんの中で、耳鳴りを主訴として来院される方は少ないのですが、健康チェック表をつけて頂くと、多くの方が耳鳴りを感じておられることがわかります。