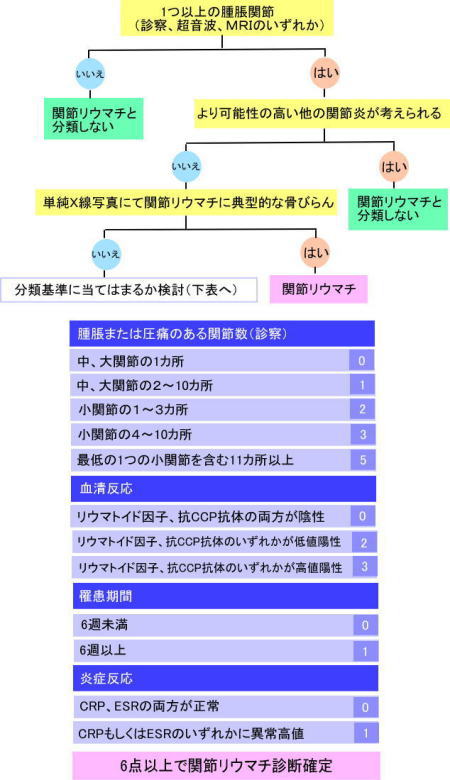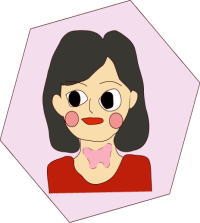年齢によって、症状が変化します。
乳児期には、頭から顔にかけて、赤いぽつぽつ、じゅくじゅくした発疹が出ます。全身に広がりやすく、首、肘のくぼみ、膝のうらなどが赤くなります。
小児期は 顔面の発疹が減り、肘や膝の関節の皮膚が厚くなり、ざらざらしてきます。かゆみをともなう発疹がつづき、ひたいや首、臀部などにも出ます。
思春期・成年期は 小児期にいったん治った患者さんが再発するケースも多く、アトピー性皮膚炎の悪化しやすい時期です。小児期とほぼ同じ部位に発疹がでますが、さらに乾燥してきます。

慢性的でかゆみの強いことが特徴です。
アトピー性皮膚炎の特徴は、まず慢性であること、一般に十年以上つづくことも珍しくありません。
つぎに、かゆみが激しいことも特徴で、このため、落ち着いて勉強ができないという子どももいるくらいです。かくとそこが象の皮膚のようになって(苔癬化)、さらにかゆくなるといった悪循環が生じます。
また、アトピー性皮膚炎の肌は抵抗力が弱いため、細菌感染やウイルス感染を起こしやすいと考えられています。
遺伝的な素因が原因となり、アレルギーやストレスが関係していると考えられています。
遺伝的な素因が考えられており、両親がアトピー性皮膚炎であったり、その家系に、喘息、アレルギー性鼻炎などがみられることが少なくありません。
また、食物や環境上の特定の抗原(ダニやハウスダストなど)によるアレルギーも病気の悪化に関係していると考えられています。しかし、1 歳以下の子は、卵、牛乳が原因になることがありますが、年長児は食事が問題になることは少ないことなど、まだ、アレルギーとの関与は十分に明らかになっていません。
その他、ストレスはかゆみを悪化させる大きな原因と考えられています。
東洋医学研究所®グループの井島鍼灸院(岐阜市)では、アトピー性皮膚炎に対して体質の改善と症状の緩和を目的とした鍼治療をさせて頂いております。
また、鍼治療によりストレスによる影響を軽減し、さらに、適切な生活指導をさせて頂くことにより症状の悪化を防ぐことができると考えます。
是非、副作用のない鍼治療を受けられることをお勧め致します。
適応症の連載を始めさせて頂いてから、現在までに73の疾患について紹介させて頂きました。その間に約6年が経過し、疾患に関する新しい情報や、鍼治療効果の研究などが報告されてきました。
そこで平成21年7月から、これらの新しい情報に加え、患者様の役に立つワンポイントアドバイスを、新しく連載させて頂きたいと思います。(2010.7.15)
アトピー性皮膚炎に対する鍼灸治療の研究をご紹介します。
全日本鍼灸学会雑誌,第59巻4号,334‐352,2009.において明治国際医療大学の江川らによる「皮膚と鍼灸-鍼灸医学における皮膚とは何か、皮膚症状に対する鍼灸の有効性を考える-」が報告されています。
その中の「アトピー性皮膚炎に対する鍼治療効果」の研究では、成人期のアトピー性皮膚炎患者45例を対象に鍼灸治療の臨床的効果について検討しています。
その結果、平均治療期間7.6ヶ月、平均治療回数24回により、掻痒感については80%の症例において改善(やや有効以上)が認められ、皮疹についても78%の症例において改善(著明に改善、改善)が認められました。
治療回数(期間)と治療効果の関連性について検討すると鍼灸治療回数が30回あるいは治療期間が1年以上にわたる場合には掻痒感や皮疹が改善する症例の割合が高く認められたことを報告をしています。
ワンポイントアドバイス
アトピー性皮膚炎の症状を悪化させる要因としては、ハウスダストや食物などのアレルゲンのほか、「手でかくこと」「ストレス」「発汗」「気候の変化」などさまざまなものがあります。
何が悪化を助長させるかは、患者さんによって異なります。また、多くの場合は、こうした要因が複合的に働いて症状を悪化させると考えられています。かゆみをコントロールする具体的な方法としては、以下のようなことに注意して下さい。
入浴、シャワーにより皮膚を清潔に保ちましょう。ただし、ごしごし洗うのは避け、皮膚が傷つかないようにやさしく洗うことが大切です。
室内を清潔に保ち、適温・適湿の環境を作りましょう。室内をこまめに掃除し、カーペットやソファを清潔に保つなど、ダニ対策もしっかり行いましょう。
ツメは短く切り、かくことによる皮膚障害を避けましょう。かくと角層が傷つき、バリア機能が損なわれるため、外部からの刺激を受けやすくなります。
過剰なストレスをためないようにしましょう。イライラしたときや逆にほっとした時に無意識にかいてしまい、それが徐々に習慣的にかくようになり、症状が悪化する大きな要因になっています。
その他に、症状を悪化させる食品を避けることや、刺激の少ない衣服を着用することも大切です。
東洋医学研究所®グループの井島鍼灸院(岐阜市)では、アトピー性皮膚炎に対して長年にわたる治療経験と多くの情報を基に、統合的制御機構の活性化と局所の症状改善を目的とした鍼治療をさせて頂いております。
さらに、それぞれの症状に合った生活習慣の改善を指導をさせて頂いております。
是非、副作用のない鍼治療を受けられることをお勧め致します。