過敏性腸症候群とは?
腹痛を伴う便通異常で、排便により症状が改善し、症状の原因となりうる器質的病変あるいは内分泌異常がないことです。精神的ストレスなどによって自律神経のバランスが崩れ、下痢や便秘、腹部不快感、腹痛などの症状が現れます。
便通の状態により、便秘型、下痢型、下痢と便秘を繰り返す混合型、上記の3つに属さない分類不能型に分類されます。

診断は?
診断基準は、過去3ヶ月間、月に3回以上にわたって腹痛や腹部不快感が繰り返し起こり、次の3つの項目のうち2つ以上があてはまることです。
①排便によって症状が軽減する
②発症時に排便頻度の変化がある
③発症時に便形状(外観)に変化がある
また、大腸ガン、潰瘍性大腸炎、クローン病などの器質的疾患を除外することが大切です。
さらに、心理的ストレスの有無など、症状の誘因となる心理的背景が診断の助けとなります。
排便症状による分類
便秘型:硬便または兎糞状便(うさぎの糞のようなコロコロした便)25%以上あり、軟便(泥状便)または水様便が25%未満のものです。
腹痛や腹部不快感を感じ、トイレに行ってもあまり便が出ません。
下痢型:軟便または水様便が25%以上あり、硬便または兎糞状便25%未満のものです。
ちょっとした緊張がきっかけで腹痛が起き、すぐトイレに行きたく なります。下痢が1日に何回も起こり、いつ便意をもよおすか分からないため生活に支障をきたすことがあります。
混合型:硬便または兎糞状便が25%以上あり、軟便または水様便25%以上のものです。
下痢が数日続いたかと思うと、次は便秘が数日続くというように症状が交互に繰り返します。
分類不能型:便性状異常の基準が上記の3つのいずれも満たさないものです。
原因は?
明らかではありませんが、消化管運動や内臓知覚の異常、緊張や不安といった心理的ストレスに対する腸管の過敏反応、消化管ホルモンなどによる消化管刺激、及び食物アレルギーなどの免疫異常などが原因として推測されます。
比較的神経質でデリケートな性格の方に多く、家庭や職場での人間関係のストレス、転居や転職による環境の変化、過労や暴飲暴食などが引き金になって症状が現れます。
東洋医学研究所®グループの井島鍼灸院(岐阜市)では、このような過敏性腸症候群に対して、全身の調整と便通の症状改善を目的とした鍼治療をさせて頂いております。
是非、副作用のない鍼治療を受けられることをお勧め致します。
2011.12.13更新
過敏性腸症候群
投稿者:
2011.12.13更新
痔
肛門周囲に分布する動脈や静脈の細い血管が集まった動静脈叢が肛門内に突出したものが痔核(いぼ痔)、肛門周囲の慢性の裂傷が裂肛(切れ痔)、肛門腺が化膿して肛門周囲の皮膚に開口したものが痔ろうです。
便秘や下痢、飲酒、喫煙、辛いものを好んで食べる、長時間同じ姿勢(立位や坐位)を続ける、妊娠・出産などが原因として考えられています。

痔核(いぼ痔)
最も多いのがこのタイプで、痔の約半分を占めます。
肛門の粘膜の下には、動静脈叢や、筋肉、線維組織などがつくるクッションと呼ばれる部分があります。
この部分は老化や排便・日常生活からくる肛門への負担から断裂するようになります。そして、排便の時などにいきむと、血管に圧力がかかるため動静脈叢が肛門内に突出したものが痔核です。
痔核の主な症状は、出血と脱出です。通常は痛みを伴わない鮮やかな色の出血であることが多いです。出血の頻度もたまに出血するだけであったのが次第に増え、ひどくなると排便のたびに出血するようになります。
脱出は始めのうちは排便の時に出て、排便の後には自然に元に戻っていますが、次第に手で押さないと戻らない状態となり、やがて排便時以外にも脱出するようになります。
裂肛(切れ痔)
排便の際に、便にこすられて、肛門の粘膜が切れるものをいいます。
裂肛は、硬い便を無理にいきんで排出したときに、伸び縮みがしにくい肛門の部分が縦に長く切れておこります。
激しい痛みと出血があります。痛みは、排便の始まり、途中、排便後まで続きます。排便後1時間ぐらいまでにおさまるのが普通ですが、半日ぐらい続くこともあります。
出血は少量のことが多いのですが、痔核の隣が切れたりすると大量の出血になります。
痔ろう
肛門内には肛門腺という粘液を出す腺が、輪を描くようにして並んでいます。この肛門腺の出口はややくぼんでいて、細菌が侵入しやすい部分です。
肛門腺は肛門を開閉する筋肉の奥にまで入り込んで存在するために、ここに細菌が侵入して感染をおこすと、普通の皮膚にできる化膿と異なり、筋肉の間に膿がたまります。この膿は肛門の組織のすきまなどの弱い部分を伝わって広がり、肛門周囲膿瘍となります。
肛門周囲膿瘍が、肛門の外側に腫れ上がってきて自然に破れると、たまっていた膿が排出され、その後にトンネル状のろう管が残ります。これを痔ろうといいます。
肛門周囲膿瘍の段階では、強い痛みと発熱がありますが、膿が排出されると急に痛みが消え、熱も下がります。
痔ろうが完成すると、細いしこりが、肛門から放射状に触れるようになり、膿がたまっていれば、ろう管から膿が出続けることになります。
そして、膿が排出されれば腫れはひきますが、やがてまた腫れてきて、破れて膿が出るということを繰り返していくことになります。
東洋医学研究所®グループの井島鍼灸院(岐阜市)では、このような痔に対し、手術療法などの必要性も考慮したうえで、鍼治療を行い、局所の血流をより良好に保つとともに、全身の調整をさせて頂いております。
また、痔の症状を改善するための、適切な生活指導もさせて頂いております。
痔で悩んでおられる方は、是非一度、副作用のない鍼治療を受けられることをお勧めいたします。
投稿者:
2011.12.13更新
下痢
下痢は、小腸や大腸で水と電解質が充分に吸収されなかったり、逆に小腸や大腸からの分泌物が増えたり、腸管の蠕動運動が亢進して、腸内容物の通過が早くなったりして起こります。
注意をしなければならない下痢は、便の中に血液、粘液、膿、消化不良物など普段見られないものが混じっている、便の色が白色、灰色、赤色、黒色、緑色など普段見たこともないような色をしている、便が腐ったような臭いがする、下痢以外に、発熱、腹痛、吐き気、嘔吐、その他の病気らしい症状を伴う場合です。
下痢だけで、上記のような症状がない場合はしばらく様子をみて心配ありません。
ただし、たびたび繰り返すときは、原因をはっきりさせる必要があります。

下痢には多くの原因があります。
下痢の原因は、急性下痢と慢性下痢に分けて考えると分かりやすいといわれています。
まず、急性下痢はその原因によって、細菌、ウイルス、寄生虫などによる感染性下痢、暴飲暴食などによる食事性下痢、特定の食品に対するアレルギー性下痢、精神的ストレスがきっかけとなって起こる心因性下痢などに分けられます。
次に、慢性下痢の約半数は、腸には何の病気もなく、その働きが異常になっている機能性下痢(過敏性腸症候群)です。残りの半数は、結腸がん、潰瘍性大腸炎、クローン病、寄生虫病、膵臓の病気、消化不良、代謝異常などが原因となっています。
東洋医学研究所®グループの井島鍼灸院(岐阜市)では、このような下痢に対して必要な場合の病院における検査を前提とし、その原因を考慮したうえで、全身の調整と、局所の症状改善を目的とした鍼治療をさせて頂いております。
また、患者さんの体質や体の状態に合わせた生活指導もさせて頂いております。
是非、副作用のない鍼治療を受けられることをお勧め致します。
投稿者:
2011.12.13更新
肝硬変
肝臓の細胞は再生力が強いため、ウイルス性肝炎やアルコール性肝障害などの原因で一部が死んでしまっても、新しい細胞が生まれてきます。
しかし、このようなことを繰り返していると、壊された場所に線維が増え、再生結節と呼ばれる隆起ができてきます。
このような変化が、肝臓全体に起こったのが肝硬変で、文字通り肝臓は硬くなり、表面がでこぼこしてきます。

原因はウイルスによるものがほとんどです。
日本では肝硬変の原因の多くはウイルスで、特にC型肝炎ウイルスによるものが最も多く、次にB型肝炎ウイルスです。ウイルス以外の原因のほとんどはアルコールによるものです。
まれな肝硬変の原因疾患として、自己免疫的な異常によりおきる原発性胆汁性肝硬変、自己免疫性肝炎、原発性硬化性胆管炎、銅の代謝異常であるウィルソン病、鉄の代謝異常であるヘモクロマトーシスなどがあります。
症状はないこともありますが、特徴的な症状もあります。
身体がだるい、食欲がないといった不定愁訴がある場合もありますが、ほとんど自覚症状のないことも少なくありません。
肝硬変に特徴的な症状は肝細胞の機能の低下と、肝臓の血流障害にともなうものに分けられます。
肝細胞の機能低下にともなう症状として黄疸、くも状血管腫(首、背中、胸などに、くもが手足を広げたような赤い斑点が出る症状)、手掌赤斑(手のひらが異常に赤くなる症状)、女性化乳房(男性の乳房が女性のように大きくなってくる症状)、肝性脳症、出血傾向などがあげられます。
肝臓に血流障害が起きると胃腸など消化管より肝臓に向かう静脈路である門脈の血圧が高くなり、それにともなう症状として、腹水、浮腫、食道静脈瘤などがあげられます。
慢性肝機能障害に対する鍼治療の研究がなされています。
慢性肝機能障害に対する鍼治療の研究は、1970年に黒野保三所長が病院に通院中の慢性肝機能障害の患者に鍼治療をしていたところ、患者から「主治医の先生から肝機能の状態が非常によくなったと言われました。」との報告を受けたのをきっかけに始められました。
そして、1975年には名古屋市立大学医学部第一解剖学教室におきまして、動物実験が開始され、1979年には(社)全日本鍼灸学会鍼灸研究ワーキンググループが発足すると同時に慢性肝機能障害班を設置し、臨床研究を本格的に始められました。
この基礎研究からは、慢性肝機能障害に対する鍼治療の予防的効果の可能性が見出されています。また、臨床研究からは、血液検査の結果や自覚症状が改善されることから慢性肝機能障害に対する鍼治療の効果が示されています
東洋医学研究所®グループの井島鍼灸院(岐阜市)では、このような研究実績に基づき長年に亘り慢性肝機能障害の治療をさせて頂いております。
慢性肝機能障害で悩んでおられる方は、是非一度、副作用のない鍼治療を受けられることをお勧めいたします。
投稿者:
2011.12.13更新
肝炎
肝炎とは、肝臓に起こる炎症のことをさします。肝炎は主な原因としてウイルスによって引き起こされます。
その他に、アルコール、薬剤、自己免疫、胆道疾患による肝炎があります。
また、肝細胞の壊れ方が、急激に起こってやがて収束に向かうものが急性肝炎で、いつまでもだらだらと肝細胞が少しずつ壊されていく状態が慢性肝炎です。
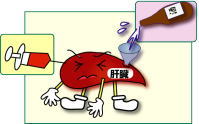
肝炎の原因で最も多いのはウイルスによるものです。
ウイルス性肝炎
肝炎ウイルスと呼ばれるウイルスの感染によって、肝臓全体の肝細胞が広い範囲にわたって破壊される病気をウイルス性肝炎といいます。
肝炎ウイルスには、A型、B型、C型、D型、E型、F型、G型などが報告されています。このうち、日本での肝炎の原因の多くはA型、B型、C型です。
主な感染経路はA型・E型は汚染された食べ物や水で、B型は出産の際や性行為など、C型は輸血の時などにウイルスの混入した血液を介したものです。
アルコール性肝炎
体質的にアルコール分解能力が低い人や、継続的に飲酒量が多い人は、肝臓で分解されるはずのアルコールが分解されず、肝細胞を破壊します。これによって炎症が引き起こされたものが、アルコール性肝炎です。
薬剤性肝炎
薬剤性肝炎には抗癌剤や解熱・鎮痛剤、工業薬剤などが直接の原因となるものと、薬剤の代謝産物により間接的にアレルギー反応が起きるものがあります。
自己免疫性肝炎
自己免疫性肝炎とは、ウイルス感染などの原因がないのに、自分の肝細胞を白血球・リンパ球が壊す慢性肝炎です。肝細胞の表面の膜にある何らかの抗原に対して免疫反応が起こった結果と考えられています。
肝炎の症状は?
どの肝炎にも共通した症状は、全身がだるく疲れやすい、食欲がない、上腹部の不快感、皮膚がかゆいなどです。
肝炎の種類や、病期によっては黄疸、発熱、頭痛、吐き気、腹が張るなどの症状が現れます。
しかし、肝臓は7割近くが切り取られても、いつも通り機能するといわれるほど我慢強いため、はっきりとした症状が現れるのは、病期がかなり進んでからになります。
肝硬変や肝癌に進行する可能性もあるため、早めの鍼治療をお勧めいたします。
慢性肝機能障害に対する鍼治療の研究がなされています。
慢性肝機能障害に対する鍼治療の研究は、1970年に黒野保三所長が病院に通院中の慢性肝機能障害の患者に鍼治療をしていたところ、患者から「主治医の先生から肝機能の状態が非常によくなったと言われました。」との報告を受けたのをきっかけに始められました。
そして、1975年には名古屋市立大学医学部第一解剖学教室におきまして、動物実験が開始され、1979年には(社)全日本鍼灸学会鍼灸研究ワーキンググループが発足すると同時に慢性肝機能障害班を設置し、臨床研究を本格的に始められました。
この基礎研究からは、慢性肝機能障害に対する鍼治療の予防的効果の可能性が見出されています。また、臨床研究からは、血液検査の結果や自覚症状が改善されることから慢性肝機能障害に対する鍼治療の効果が示されています。
東洋医学研究所®グループの井島鍼灸院(岐阜市)では、このような研究実績に基づき長年に亘り慢性肝機能障害の治療をさせて頂いております。
慢性肝機能障害で悩んでおられる方は、是非一度、副作用のない鍼治療を受けられることをお勧めいたします。
投稿者:
2011.12.13更新
脂肪肝
肝臓は体の中でとても重要な働きを担っている臓器といえます。胃や腸で消化された栄養分は門脈を通って肝臓に送られます。肝臓ではそれを分解・合成・貯蔵して、体が利用しやすいように供給しています。
また、肝臓には消化を助ける胆汁を作る働きや、アルコールや薬を分解する働き、体に有害な物質を無毒化するなどの働きがあります。

脂肪肝とはどんな病気?
正常な肝臓でも3~5%の中性脂肪を含んでいますが、5%を超えた状態を脂肪肝といいます。
脂肪肝は、30~70才代に多く、男性に多く発症しています。
以前、脂肪肝は、それほど深刻な病気とは考えられていませんでした。しかし、最近、脂肪肝から肝炎、肝硬変、肝臓癌にまでなる可能性があることがわかったため、注意しなければならない疾患と考えられるようになってきています。
不摂生をすると1~3ヶ月で発症するといわれています。
脂肪肝の原因は、食べ過ぎや、アルコールの飲みすぎ、糖尿病、無理なダイエットなどです。頻繁に暴飲暴食をする人は1~3ヶ月で脂肪肝になるといわれています。
多くの場合、自覚症状はないことが多いです。
肥満であることや、血液検査でAST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、総コレステロール値、中性脂肪値などの高い場合には脂肪肝が疑われますが、多くの場合、脂肪肝には自覚症状がありません。しかし、肝臓に脂肪がたまると、内部の血液循環が悪くなり、それにともなって肝機能が低下していきます。その結果、体が疲れやすくなったり、だるくなったりすることもあります。
慢性肝機能障害に対する鍼治療の研究がなされています。
慢性肝機能障害に対する鍼治療の研究は、1970年に黒野保三所長が病院に通院中の慢性肝機能障害の患者に鍼治療をしていたところ、患者から「主治医の先生から肝機能の状態が非常によくなったと言われました。」との報告を受けたのをきっかけに始められました。
そして、1975年には名古屋市立大学医学部第一解剖学教室におきまして、動物実験が開始され、1979年には(社)全日本鍼灸学会鍼灸研究ワーキンググループが発足すると同時に慢性肝機能障害班を設置し、臨床研究を本格的に始められました。
この基礎研究からは、慢性肝機能障害に対する鍼治療の予防的効果の可能性が見出されています。また、臨床研究からは、血液検査の結果や自覚症状が改善されることから慢性肝機能障害に対する鍼治療の効果が示されています。
東洋医学研究所®グループの井島鍼灸院(岐阜市)では、このような研究実績に基づき長年に亘り慢性肝機能障害の治療をさせて頂いております。
慢性肝機能障害で悩んでおられる方は、是非一度、副作用のない鍼治療を受けられることをお勧めいたします。
投稿者:
2011.12.13更新
便秘
大腸での排便のしくみは?
小腸で栄養分が吸収された食物の残りは、大腸に送られる時点では水分を多く含んでいて、液状から泥状の状態です。
その後、腸内容物は、大腸の蠕動(ぜんどう)運動によって、からだの右側に位置する上行結腸、左側に位置する下行結腸へと運ばれていくうちに、濃縮され、水分などが大腸粘膜から吸収され固形化され、S状結腸へと運ばれます。
S状結腸にある程度の量の腸内容物がたまると、重力の関係や食物摂取による胃の刺激がきっかけとなって大蠕動運動がおこり、腸内容物がいっきに直腸まで運ばれます。
このときに加わる直腸粘膜への刺激が脳へ伝えられて便意を感じ、排便の姿勢をとると、肛門挙筋が収縮し、肛門括約筋がゆるんで便の排泄が行われるわけです。

便秘の原因には大きく分けて2種類あります。
排便が24~48時間の間隔で規則正しく行われていれば正常です。48時間以上排便がなかったり、1日1回排便があっても、量が少ない時、便がすっきり出た感じがない時、便意があっても排便ができず苦しんだりする場合を便秘といいます。
この便秘には、器質性便秘と機能性便秘の2種類があります。
①器質性便秘
大腸に慢性腸炎、腸閉塞、ガンなどの病気があって、内腔が狭くなって腸内容物が通りにくくなっておこるものや、腸の長さや大きさの異常によっておこる便秘(先天性大腸過長症)をいいます。
②機能性便秘
大腸の蠕動運動が弱かったり(弛緩性便秘)、逆に蠕動運動が活発過ぎたり(けいれん性便秘)、排便のさいに肛門括約筋が開くという排便反射がうまく働かなかったり(直腸型便秘)などの、大腸の働きが異常になるためにおこる便秘をいいます。
脳と大腸とをつなぐ神経の伝達経路に障害があっておこることもあるのですが、大部分は、病気などの原因はなく、便秘が習慣になってしまったものです。このことから、常習性便秘とも習慣性便秘ともいいます。
また、汗が多量に出たり、水分の摂取量が足りなくて、便の水分が足りない場合や、食物繊維が少ない食事に偏り過ぎた場合、環境の変化やストレス、運動不足などによる便秘があります。
東洋医学研究所®グループの井島鍼灸院(岐阜市)では、便秘に対して鍼治療を施し、全身の調整をするとともに、腸の働きを良くする治療をさせて頂いております。
さらに、便秘を改善するための適切な生活指導もさせて頂いております。
是非、副作用のない鍼治療を受けられることをお勧め致します。
投稿者:
2011.12.13更新
胃酸過多症
胃液の酸度が高く、酸症状(胸やけ、げっぷ)があります。
胃液の中に含まれている塩酸の酸度が異常に高いとき、これを胃酸過多といい、それによって胸やけ、げっぷ、呑酸
(すっぱい液体が胃から口中にこみ上げること)などのいわゆる酸症状がある場合を、胃酸過多症といいます。

原因はいくつか考えられていますが、よくわかっていません。
原因としては、胃粘膜の胃酸を分泌する細胞が多いことや、胃酸分泌を促す中枢神経からの刺激に対する感受性の亢進、胃液分泌の促進と抑制を調節する神経(迷走神経、交感神経)やホルモン(ガストリン、セクレチン)の異常などが考えられていますがその仕組みについてはまだよくわかっていません。
また、胃酸過多症は、よく慢性胃炎や胃・十二指腸潰瘍にともなっておこります。
食後1~2時間で症状が出るのが普通です。
食後に酸度の高い胃酸液が大量に分泌されるため、胃酸過多症の症状は食後1~2時間でおこるのが普通です。
胃酸過多かどうかは、口または鼻から細いチューブを飲み込み、胃液を採取して胃液の酸度を調べて診断されます。
主食はやわらかく炊いた米飯がよく、刺激物は避けましょう。
米飯、めん類、パンなどの糖類は胃酸の分泌を促すことが少ないので、胃酸過多症にはよい食べ物と言われています。
熱すぎるものや、冷たすぎるもの、硬い線維のある野菜などは胃酸の分泌を促しますので避けましょう。また、香辛料や濃いコーヒー、酒、たばこなどの刺激の強いものも避けましょう。
鍼と超音波の併用療法
-胃腸疾患に対する効果-
昭和44年4月1日より昭和47年3月1日までの3年間に東洋医学研究所®に来院された患者の中の1336例について、黒野所長が鍼と超音波の併用療法による各種疼痛疾患に対する効果などを詳細に研究し、これを症病別に集計しました。
その中で胃腸疾患に対しての結果は、患者188名のうち124名が著効18名が有効、13名が比較的有効、15名がやや有効、18名が無効となり、170名の方に効果がみとめられたため、有効率は90.4%でした。
以上のことから、上記のような胃腸疾患に対する鍼治療の効果が実証されています。
さらに、東洋医学研究所®グループの井島鍼灸院(岐阜市)では上記を参考に30年間に亘り胃腸疾患に対する鍼治療を行い好成績をあげています。
是非、副作用のない鍼治療を試してみて下さい。
投稿者:
2011.12.13更新
胃・十二指腸潰瘍
胃や十二指腸の内側をおおっている粘膜の一部に、ただれ、壊死などの変化がおこり粘膜がはがれて欠損ができる病気を胃・十二指腸潰瘍といいます。食物を消化する胃酸やペプシンは攻撃因子と呼ばれ、粘膜を保護する粘液の分泌は防御因子と呼ばれています。健康な人では、この両者のバランスがうまくとれています。ところが、精神的・肉体的ストレスなどにより、このバランスが崩れると胃酸やペプシンが胃や十二指腸の粘膜を消化してしまい潰瘍ができると考えられています。
また、最近では粘膜保護作用のあるプロスタグランジン(生体内で合成される生理活性物質)の減少や、ヘリコバクター・ピロリ菌の関与も考えられています。
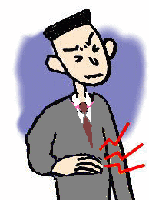
程度がひどくなると、たいへんです。
胃・十二指腸潰瘍のごく初期には、粘膜の表面がただれて、粘膜に浅い孔ができる程度ですが、進行すると、この孔が粘膜をえぐって筋肉層におよびます。更にひどくなると、胃や十二指腸のいちばん外側をおおっている漿膜にまで達し、ときには漿膜を突き破ってしまうこともあります。
発生する潰瘍の数は、一個のこともありますし、数個のこともあります。潰瘍一個の大きさは、直径数ミリメートルの小さなものから、直径数センチメートルもある大きなものまでいろいろです。
腹痛、出血、過酸が三大症状です。
腹痛、出血(吐血、下血)、過酸症状(胸やけ、げっぷなど)が、胃・十二指腸潰瘍の代表的な症状で、潰瘍の三大症状ともいわれます。
しかし、症状の現われ方は人によってまちまちで、三つの症状が同時におこる人もいれば、腹痛だけ、出血だけの人もいます。この他、吐きけや嘔吐、食欲不振、便秘などがおこる場合もあります。
しかし胃潰瘍ではまったく無症状の人も珍しくなく、いきなり吐血、下血することもありますし、胃の検診のさいに初めて潰瘍が発見される人も少なくありません。
治りやすいが、再発もしやすい病気です。
胃・十二指腸潰瘍は治りやすい病気といわれています。治療を受けなくても、自然に治ってしまうこともしばしばあります。
しかし、同時に再発もしやすい病気で、過半数は再発するといわれています。したがって、この病気を放置しておいたり、あるいは完全に治さずに治癒と再発をくり返しているうちに、潰瘍が進行して、危険な合併症をおこすこともあります。
鍼と超音波の併用療法
-胃腸疾患に対する効果-
昭和44年4月1日より昭和47年3月1日までの3年間に東洋医学研究所®に来院された患者の中の1336例について、黒野所長が鍼と超音波の併用療法による各種疼痛疾患に対する効果などを詳細に研究し、これを症病別に集計しました。
その中で胃腸疾患に対しての結果は、患者188名のうち124名が著効、18名が有効、13名が比較的有効、15名がやや有効、18名が無効となり、170名の方に効果がみとめられたため、有効率は90.4%でした。
以上のことから、上記のような胃腸疾患に対する鍼治療の効果が実証されています。
さらに、東洋医学研究所®グループの井島鍼灸院(岐阜市)では上記を参考に30年間に亘り胃腸疾患に対する鍼治療を行い好成績をあげています。
是非、副作用のない鍼治療を試してみて下さい。
投稿者:
2011.12.13更新
胃炎
胃炎は以前、その定義があいまいでしたが、内視鏡検査の進歩によって他の病気と区別することや、どの型の胃炎であるかが正確に診断されるようになりました。
胃炎は、胃の内壁をおおっている粘膜に炎症のおこる病気ですが、原因や経過、炎症の状態などから、急性胃炎と慢性胃炎に分けられます。

急性胃炎
急性胃炎は、はっきりした原因があっておこるものです。
その原因により急性外因性胃炎と、急性内因性胃炎に分けられます。
急性外因性胃炎
①急性単純性胃炎=暴飲暴食や酒の飲みすぎが原因となって
おこり、軽い吐き気、腹部圧迫感、ときに嘔吐があります。
②急性腐食性胃炎=腐食剤や農薬などを飲んだことが原因で、
のどや胸の痛み、胃が焼けるようなけいれん性の痛みがあり
激しい吐き気、嘔吐があります。
急性内因性胃炎
①急性化膿性胃炎=ピロリ菌などの感染によって、粘膜下層に
化膿性の炎症が起こるため、高熱を発し、腹痛も激しいもの
になります。
②急性感染性胃炎=ジフテリア、インフルエンザなどの感染症
に合併して発病し、強いけいれん性の痛みがあります。
③アレルギー性胃炎=魚介類、薬剤などに対する過敏反応な
どでおこることがあります。頻度はまれな病気です。
慢性胃炎
長い間に繰り返された胃粘膜のびらんとその修復の結果として、胃粘膜や胃腺に萎縮が生じた状態です。正しくは慢性萎縮性胃炎と呼ばれます。
慢性胃炎患者の胃粘膜からピロリ菌が高率に検出されることから、主要な病因因子の1つと考えられています。また、食事、薬剤、加齢、自己免疫などの要因が重なっておこるとも考えられていますが、はっきりわかっていません。
胃粘膜や胃腺の萎縮の結果、長期にわたる食欲不振、吐き気、嘔吐上腹部不快感などの症状が続きます。
鍼と超音波の併用療法
-胃腸疾患に対する効果-
昭和44年4月1日より昭和47年3月1日までの3年間に東洋医学研究所®に来院された患者の中の1336例について、黒野所長が鍼と超音波の併用療法による各種疼痛性疾患に対する効果などを詳細に研究し、これを症病別に集計しました。その中で胃腸疾患に対しての結果は、患者188名のうち124名が著効、18名が有効、13名が比較的有効、15名がやや有効、18名が無効となり170名の方に効果がみとめられたため、有効率は90.4%でした。
以上のことから、上記のような胃腸疾患に対する鍼治療の効果が実証されています。
さらに、東洋医学研究所®グループの井島鍼灸院(岐阜市)では上記を参考に30年間に亘り胃腸疾患に対する鍼治療を行い好成績をあげています。
是非、副作用のない鍼治療を試してみて下さい。
投稿者:
ARTICLE
SEARCH
ARCHIVE
- 2025年07月 (1)
- 2025年06月 (3)
- 2025年05月 (1)
- 2025年04月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (3)
- 2024年09月 (3)
- 2024年08月 (3)
- 2024年07月 (4)
- 2024年06月 (5)
- 2024年05月 (4)
- 2024年04月 (4)
- 2024年03月 (1)
- 2024年02月 (2)
- 2024年01月 (3)
- 2023年12月 (7)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (2)
- 2023年09月 (2)
- 2023年01月 (3)
- 2022年03月 (2)
- 2022年02月 (1)
- 2021年05月 (1)
- 2020年06月 (5)
- 2020年05月 (5)
- 2020年04月 (1)
- 2020年01月 (1)
- 2019年12月 (1)
- 2017年12月 (2)
- 2017年11月 (3)
- 2017年10月 (3)
- 2017年09月 (1)
- 2014年06月 (1)
- 2014年05月 (1)
- 2014年03月 (1)
- 2012年10月 (1)
- 2012年09月 (1)
- 2012年08月 (5)
- 2012年07月 (2)
- 2012年06月 (5)
- 2012年04月 (3)
- 2012年03月 (6)
- 2012年02月 (4)
- 2011年12月 (66)
CATEGORY
- 井島鍼灸院ブログ (0)
















