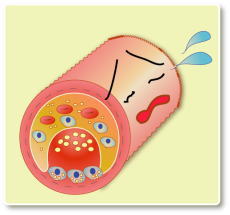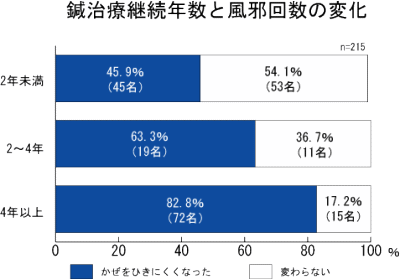腎臓は、糸球体で血液を濾過して、不必要な成分は尿として捨て、必要な成分は尿細管で再吸収して血液に送り返すという仕事を行っています。
この糸球体と尿細管を合わせてネフロンと呼んでいます。
ネフローゼ症候群は糸球体に起こった障害のために、多量のタンパク質が濾過されてしまい、尿細管の再吸収が間にあわなくなって、大量(1日3.5g以上)のタンパク質が尿と一緒にもれ出てしまう病気です。
多量のタンパク尿が続くと、血液中のタンパク質が少なくなる低タンパク血症(血液中の血清総タンパク量が6.0g以下)になり、コレステロールが多くなって、高コレステロー血症になります。また、血管から水や電解質がもれ出て、これが皮下にたまり浮腫(むくみ)も起こってきます。

原因は?
ネフローゼ症候群は、糸球体の障害によって起こるのですが、糸球体に起こった障害の原因が分からないものが原発性ネフローゼ症候群で、いちばん多く、特に子供はほとんどが原発性です。
成人の場合は約半数が急性腎炎と慢性腎炎から起こります。年齢が増すにつれて、ループス腎炎(全身性エリテマトーデスの腎病変)や、糖尿病性腎症、痛風などの原因による、続発性ネフローゼ症候群が増えてきます。
目で見てわかる症状はむくみです。
血液中のタンパク質が、多量に尿中にもれ出してしまうと、血液中のタンパク質濃度が低下し、血管内の膠質浸透圧が周囲よりも低くなります。
そのために、血液中の水と塩類が血管外に出て、血管内と周囲の浸透圧を同じに保とうとします。血管外へもれ出た水や塩類は、組織と組織の間にたまりますが、これが皮下におよんでむくみとなるのです。
初期は、まぶたがむくむ程度なので見逃しやすいですが、足にむくみが出て靴がはきにくくなったり、靴下のあとが消えなかったりして気づくことがあります。
さらにひどくなると、腹水、胸水、咳、痰、呼吸困難などが起こります。また、むくみが急速に起こってくるときには尿量が減り、乏尿や無尿になることもあります。
東洋医学研究所®グループの井島鍼灸院(岐阜市)では、このようなネフローゼ症候群に対して全身の調整と症状の改善を目的とした鍼治療をさせて頂いております。
是非、副作用のない鍼治療を受けられることをお勧め致します。