めまいとは?
めまいは、からだのバランスを保つ機能に障害が起こると生じます。からだの平衡をつかさどる器官には三半規管、耳石器、前庭神経、脳幹、視床、大脳皮質があります。
めまいには大きく分けて、自分の身体や周囲がぐるぐる回っているように感じる回転性めまいと、身体がふらついたりまっすぐ歩けない浮動性めまいがあります。
これが、耳の病気や脳の病気などにより障害されると、バランスが崩れ、めまいが起こります。
めまいを訴える人の数は、厚生省の国民生活基礎調査によると、約240万人にのぼっています。

回転性めまい
運動感覚や位置感覚の異常を、かなりはっきり自覚するめまいで、自分の身体や周囲のものがぐるぐる回転するように感じる回転感、エレベーターに乗っているように感じる昇降感、床が揺れて歩けないように感じる傾斜感などを示すめまいのことをいいます。
回転性めまいは、内耳や前庭神経に関わる異常によって引き起こされることが多く、原因となる病気にはメニエール病、前庭神経炎、突発性難聴などがあります。そのため、難聴、耳閉感、耳鳴りなどの聴覚症状を伴うことがあります。
回転性めまいは、発症が急激な場合が多く、吐き気、嘔吐がみられ、頭痛、手足のしびれ、麻痺、ろれつが回らない、意識がなくなるなどの症状がある場合は、脳に障害が起こっている可能性もありますので早急に対処することが大切です。
浮動性めまい
回転性めまいと比較すると、漠然としており、体がふわっとする感じ、頭の中で何かが揺れ動く感じ、自分の体がなんとなく不安定な感じ、地面や床が揺れ動く感じなどのように、あまりはっきりとしない状態のめまいのことをいいます。
浮動性めまいは、内耳や前庭神経以外の中枢神経の異常、全身的な異常、婦人科や神経内科で扱う異常などによって起こることが多く、原因となる病気には、低血圧、高血圧、更年期障害、不安神経症などがあります。
浮動性めまいは、立ちくらみ、脱力感、頭痛を伴うことがあり、身体や頭を動かしたときに増強することがあるため、楽な姿勢をとり、安静を保つことが大切です。
東洋医学研究所®グループの井島鍼灸院では、このようなめまいに対して、専門医療機関と連携し、全身の調整と局所の症状改善を目的とした鍼治療をさせて頂いております。

また、めまいは疲労やストレスなどにより症状が出やすくなったり、強くなることが知られており、これらを防ぐためにも、 是非、副作用のない鍼治療を受けられることをお勧め致します。





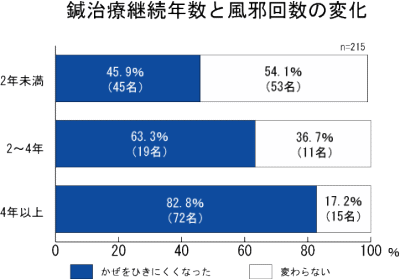





 腰は、体重を支えるのに最も大きな役割を受け持ち、体を曲げ伸ばしするとき、物を持つときに、いちばん負担の加わるところです。
腰は、体重を支えるのに最も大きな役割を受け持ち、体を曲げ伸ばしするとき、物を持つときに、いちばん負担の加わるところです。 顔面神経麻痺に対して、本当に鍼治療は効果があるのかという質問を受けることがあります。
顔面神経麻痺に対して、本当に鍼治療は効果があるのかという質問を受けることがあります。











