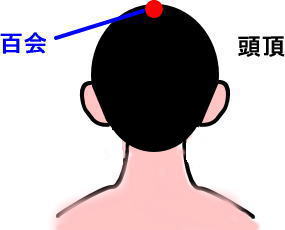
東洋医学研究所の黒野保三先生には、毎月1回健康しんぶんを発刊して頂いています。
その中で福田裕康先生が担当されている「シリーズ東洋医学」を紹介させて頂きます。
今回は平成25年2月1日に発刊される第21刊健康しんぶんから、「経穴について(3)」です。
2011年に「オートノミックニューロサイエンス」という雑誌に「Acupuncture to Danzhong but not to Zhongting increases the cardiac vagal omponent of heart rate.」というタイトルで東洋医学研究所の黒野保三所長の研究結果が掲載されました。
この論文には、集大成ともいうべき黒野所長が今まで研究され治療されてきた鍼治療の方法の裏付けとなる基礎データが示されました。
では、この過程を振り返ってみましょう。
昨年十二月のこの欄で、経穴(合谷穴)には深さがあることを紹介しました。
では、そのことは何をもっていうことができたのでしょうか?合谷という経穴は手の親指と人差し指の付け根にあります。そこを鍼刺激した時に遠く離れた胸部と腹部で反応が出ることが分かりました。
胸部や腹部の皮膚をピンチで強くはさんでいるのに痛みを感じなくなったのです。これは、閾値があがって感覚が鈍くなったことを意味します。
つまり、鍼刺激は、鍼を刺した手の部分だけではなく、全身に影響を与えることが示されたわけです。
そして、最も効率よくこの反応を起こさせる深さは5~7ミリでありました。
鍼を刺した五~七ミリの深さのところは、筋肉を覆っている膜を破るのではなく、圧をかけて押した状態(筋膜上圧刺激)であるということが明らかとなりました。
このことを証明するために、黒野所長の実験には工夫の跡がたくさんみられます。同じことをやれば同じ結果が出るという再現性を実現するために、手の位置が毎回同じ場所に当てられるようにビール瓶を用いて手を固定したりすることや、それでも毎回同じような結果が得られないことがあった時に、その基礎がしっかりしていたので他のことを検討できました(これは後に紹介しますが、治療頻度の決定につながりました)。
そして、冒頭で紹介した論文につながるのですが、この方法(筋膜上圧刺激)で行なった鍼治療の効果とその効果を発揮する仕組みの一つが解明されました。
これが鍼治療研究における大きな前進となることは間違いありませんでした。
【投票ボタン】2つのランキングに参加中














