2012.08.24更新

手軽に健康法が楽しめるウォーキング。休日の朝夕は、全国の至る所でウォーキング姿が見られます。
この時、歩くリズムに呼吸のリズムを合わせるだけで、疲労感と息切れが激減します。
1歩目と2歩目の足を出すときに合わせて口から息を2回吐き、次の2歩目に合わせて鼻で2回吸います。
足を出すタイミングに合わせ「吐く→吐く→吸う→吸う」を繰り返すのです。
すると脳内のホルモンの「セロトニン」という物質が放出され、集中力が高まり、痛みや疲労、ストレスが抑制されるのです。
毎日20分から30分のウォーク呼吸法を2,3ヶ月続けると、歩いていない時でも脳内のセロトニン量が増えて、プレッシャーに強い性格になります。
会議の前などでも、下腹がへこむぐらいゆっくりと息を吐く「腹式呼吸」を規則的に5,6回やるだけで気分がリラックスし、集中力が高まります。
最も手軽な健康法は、能率向上法でもあるのです。
是非、一度試してみて下さい。
投稿者: 井島鍼灸院
2012.08.21更新
東洋医学研究所®HPの中で海沼英祐先生の書かれたコラムを紹介させて頂きます。
東洋医学研究所®グループ 海沼鍼灸院
院長 海沼英祐 先生
○はじめに
近年、「人生を、より良く生きる」という考えのもと、健康に生きるために免疫学へ注目が集まっています。免疫力という言葉をよく耳にしますが、免疫力とはいったい何なのでしょうか?免疫力が上がった状態とは、どんな状態なのでしょうか?
○免疫力とは?
免疫系は、細菌やウイルスなど、自分以外のもの(異物)や自分の害になるもの(外敵)が侵入してくると、それを認識して排除しようとするシステムです。
ガン細胞のように、自分とは違う組織に対しても、戦って排除しようとします。この免疫系の主役が、白血球と呼ばれる細胞です。
白血球は、血液成分のひとつです。血液は、血液細胞である有形成分と、血漿である液体成分に分けられます。有形成分の多くは赤血球ですが、それ以外に血小板と白血球が存在します。
白血球には様々な種類がありますが、大きくは、マクロファージ(約5%)、顆粒球(約60%)、リンパ球(約35%)に分類できます。
これらの白血球は、それぞれで役割が異なっています。必要に応じて、それぞれの白血球が連携プレーを行って異物や外敵を排除します。この異物や外敵を排除しようとする力が、免疫力と呼ばれているものです。
○免疫力が上がった状態とは?
血液検査に、WBC(白血球数)という項目があります。基準値は、血液1ml中3600~8000個と、かなり幅があります。これは、白血球の数が常に一定ではなくて、かなり変動するからです。
通常は、基準値に収まる個数ですが、風邪をひいたり、怪我をしたり、ガンができたりすると、防御反応で白血球が急増します。時には、1万個にも2万個にも増えることがあります。
変動するのは、白血球の個数だけではありません。先に述べたように、白血球には、顆粒球、リンパ球、マクロファージがあります。
このうちマクロファージは数が少なく、血液中の白血球の95%を占めているのは顆粒球とリンパ球になります。
平均的な比率は、顆粒球が60%くらいで、リンパ球が35%くらいとなっています。基準値の比率では、顆粒球が40~71%ほどで、リンパ球が27~47%ほどです。
このように、顆粒球とリンパ球の比率も平均的な比率であって、常に一定というわけではありません。1日のうちでも、ほぼ一定のパターンで比率は変動しています。
基本的に、活動している昼間は顆粒球の比率が大きくなり、夜のゆったりとした時間帯はリンパ球の比率が大きくなります。
それ以外でも、季節や気圧の変化などの環境も、比率の変動に影響を与えていますし、体調によっても割合は変化します。
正常な比率の範囲内でいる状態が、白血球が連携プレーを行うのに一番適した状態であるため、この比率が正常範囲内からはずれると、体内に何らかの異常が起きている可能性があります。
比率の変動は、白血球の大半を占める顆粒球の増減が大きな影響を与えています。
顆粒球は、寿命が2日間と非常に短いため、1日に半分の顆粒球を補給しなくてはなりません。そのため、ちょっとした環境や体調変化によって顆粒球が増減すると、その影響が白血球の比率に大きく影響を与えます。ちなみにリンパ球の寿命は7日前後と、環境や体調に合わせて比率と数がゆっくりと変動しています。
先に述べた白血球数の増加と、状況に応じた白血球の比率変動が免疫力の上がった状態に深く関連します。体内に異物や外敵が侵入してきたときに素早く対応して、白血球数を増加させ、異物や外敵の種類に応じて白血球の比率を変動させて対応するからです。
さらに、自分の体調が良い状態にあるときは、素早い免疫系の対応が期待できます。また体調が良いときの方が、自身の体内で生み出される白血球も、元気で強い白血球が生み出されます。
このように、免疫力の上がった状態とは、自分の心と体が安定かつ充実した状態で、異物や外敵が体内に侵入してきたときに素早く対応できるような白血球数と白血球比率を保った状態といえるかと思います。
○おわりに
鍼灸治療が免疫力の増強に良いとされる大きな理由は、鍼灸治療を受けることにより、心と体の安定した状態・充実した状態を得られることにあります。元気な体は、強い白血球を産生し、異物や外敵の侵入時には素早い免疫系の対応を可能にします。
東洋医学研究所®黒野保三先生の生体制御療法は、まさにそうした体作りを考慮にいれた治療法です。ぜひ生体制御療法を受けてみてはいかがでしょうか。
参考文献:安保徹の病気にならない免疫のしくみ(ナツメ社) 安保徹
長生き健康「鍼」(医学書院)黒野保三
鍼刺激のヒト免疫反応系に与える影響(Ⅰ~Ⅵ) 黒野保三
投稿者: 井島鍼灸院
2012.08.16更新
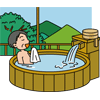
8月14日(火)に、初めて岐阜県揖斐郡揖斐川町にある「いび川温泉 藤橋の湯」に行ってきました。
営業時間...10:00~21:00(最終受付20:30)
定休日...毎週木曜日(木曜日が祝日の時はその翌日)
料 金...大人500円(12歳以上) 小人(3歳以上12歳未満)300円
午前11時頃に着いたのですが、わりとすいており、ゆっくり入れました。
出る頃には少し混んできました。
露天風呂から美しい山の緑が見え、帰りにはおいしい二八そばを食べることができました。
8月15日(水)には、治療室のワックスがけをした後、こちらも初めての岐阜県揖斐郡大野町にある「根尾川天然温泉 湯元おおの温泉」に行ってきました。
営業時間...10:30~20:45(最終受付20:00)
定休日...毎週金曜日(祝日の場合は前日休)
料 金...大人500円 小人(小学生)400円 幼児200円
岐阜市の中心部から約30分で着きました。ただ、道がややわかりにくいため注意が必要です。
ぬるっとしたお湯は、とても気持ちよく、出た後も壮快でした。
以前にも紹介させて頂きましたが、温泉はストレス発散、免疫力アップなどに効果があり、とてもよい健康管理の方法だと思います。
岐阜県には本当にたくさんの温泉があり心から感謝します。
投稿者: 井島鍼灸院
2012.08.11更新

仕事の量、質に加えスピードも大きくアップ、さらにまったく新しい業務への対応も迫られる現代。
私たちの多くはストレスと向き合っています。
ストレスがない人生はあり得ません。
ストレスの対処法を身に付けることは、現代人にとって不可欠といえます。
そのストレスやプレッシャーを「ワクワク」感に変換し、結果を出した代表格がイチロー選手です。
厚生労働省ではバランスのとれた心の健康こそ「イキイキエお生きる」ための条件として、次の四つの要素を挙げています。
1.自分の感情に気付いて、他者に表現ができる。
2.状況に応じて適切に考え、現実的な問題解決ができる。
3.他人や社会とかかわりを持ちながら、建設的で良い関係を築ける。
4.人生の目的や意義を見出し、主体的に人生を選択する。
豊かな精神生活、適切な運動を心がけると共に、ストレスをバネにして人生の楽しみを発見する強靭さを、プラス思考の言動で培いたいと思います。
そうすることで、調子を崩しておられる方々のお役により一層立てるようになりたいと思います。
投稿者: 井島鍼灸院
2012.08.10更新

長谷川病院院長の柏瀬宏隆先生がストレスに負けない6か条を提言されています。
1.汝自身をよく知る
自分の性格特徴をよく把握して、それが行き過ぎにならないように心がける。
2.休息と睡眠を
生活上の変化があるときには注意をし、休息や睡眠を十分にとる。
3.ゆとりのある生活
柔軟で余裕のある生活を心がける。秩序に縛られず、ゆとりある八分目の生活を。
4.完璧にこなそうとしない
物事を処理する時には、順位をつけて大切な事柄から処理する。「あれもこれも」ではなく
「あれか、これか」にする。
5.一人で抱えない
他人に任せられることは任せ、自分の負担を軽減する。
6.自分を大切に
他人の評価に縛られないこと。他人の眼を意識しすぎないように心がけ、自分を大切にする。
ストレス解消法
1.休息型 2.運動型 3.親交型 4.娯楽型 5.創作型 6.内省型 7.気分転換型
投稿者: 井島鍼灸院
2012.08.09更新
第30回公益社団法人生体制御学会学術集会
市民公開講座 参加無料 市民公開講座ポスター
主 催:公益社団法人生体制御学会
日 時:平成24年8月26日(日) 午後1時~3時20分
会 場:名古屋市立大学医学部講堂(図書館3階)
内 容
第30回記念講演
演題:「健康と長寿 自己管理と東洋医学」
講師:公益社団法人生体制御学会名誉会長 黒野保三
司会:藤田保健衛生大学医学部内科 客員教授 松本美富士
特別講演
演題:「リウマチ、自己免疫疾患および悪性腫瘍の背景にある共通する分子機構について」
講師:名古屋市立大学大学院医学研究科細胞分子生物学
教 授 岡本 尚
司会:公益社団法人生体制御学会 会 長 中村弘則
学術集会事務局:公益社団法人生体制御学会事務所
〒464-0848 名古屋市千種区春岡2-23-10
TEL(052)751-9144 FAX (052)751-8689
事前の予約はございません。
是非、多くの方のご参加をお待ちしております。
投稿者: 井島鍼灸院
2012.08.08更新

「ほめる人より叱る人」とはよく耳にする言葉です。人は誰でもほめられれば嬉しいものです。
反対に叱られたり批判されたりした場合、往々にして人は他人の言葉に対して素直になれないものです。
けれども叱られたことを根に持ったり、批判した人を恨んだりしていては進歩向上はのぞめません。
昔から「良薬口に苦し」といわれるように、本当の進歩や成長の鍵は聞く人間にとっては耳の痛い言葉の中に隠されていることが多いものです。
投げかけられた言葉をプラスの要素にするか、マイナスの要素にするか、すべては受け止める人間の心にかかっています。
叱られたりするのは自分の中にそれだけの原因があるから、と謙虚な気持ちで受け止めれば、人の言葉にも素直になれるし、批判や叱咤(しった)の言葉の裏にあるその人の優しさや励ましにも気づくことでしょう
謙虚さはときに大いなる飛躍へのステップとなりえるのです。
私も叱られ上手になりたいと思います。
参考文献 倫理研究所 「職場の教養」
投稿者: 井島鍼灸院
2012.08.07更新
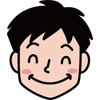
毎日を明るく朗らかな心で暮らすことの大切さは、みんなが知っていることですが、簡単には実行できません。
明るさを失うと心が鈍り、気おくれして決断力が鈍ってしまいます。これではうまくゆく事も失敗します。
ともかく人は物事が順調に進んでいるときには明るくなり、壁やトラブルに出合ったときには暗くなりがちですが、実は逆で、順調の時には慎重に行動し、逆風の時にこそ、それを乗り越える明るさを持たなくてはならないのです。
患者様からクレームを頂戴した時や師匠に叱られたときなど、「また失敗してしまった」意気消沈するのと、「至らない点を教えていただき、ありがとうございます」と笑顔で受け止めるのとでは、自ずと結果は違ってきます。
明るい心を持つためには①目覚めたらサッと起きる ②元気よくあいさつする ③気づいたらすぐ実行する などの実行が効果的です。
私自身も、どんなときでも明るさで、周囲を照らせる人間になりたいと思います。
参考文献 倫理研究所 「職場の教養」
投稿者: 井島鍼灸院
2012.08.05更新
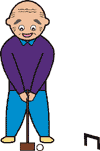
師匠の黒野保三先生や、財団法人聖路加国際病院理事長の日野原 重明先生の日常生活を拝見すると、そのバイタリティーに驚き、どうして長年にわたり続けらえるのか不思議にさえ感じます。
東京都老人総合研究所の下仲順子先生は、百歳の方を対象に性格の調査研究をされています。
下仲先生によれば、無事百歳を迎えた長寿者に、ある程度共通する性格は「自分が定めた目標に向かってできる限りの努力はするが、あせったりイライラせず、一つのことを着実に行っている」だそうです。
この点について山梨医科大学の渋谷昌三教授も「長寿者はその性格からすると、四計に従って、それを実行してきた人たち。身体が健康であることのほかに、充実感のある人生を計画的に生きることが長寿の源泉」と語ります。
四計とは「一日の計」「一年の計」「一生の計」「一家の計」をいいます。
いずれも始めが肝心で、しっかり計画を立て、着実に実行することにより得られる充実感が、長寿の大きなポイントということでしょう。
常に目標を持ち計画的に生きることで長寿を保ち、人や社会に貢献していきましょう。
私自身も努力していきたいと思います。
参考文献 倫理研究所 「職場の教養」
投稿者: 井島鍼灸院
2012.08.04更新

昔から「病気治しは癖直し」といわれるように、病気には身体の癖、食べ物の癖、心の癖の3つが深くかかわっています。
体の癖は生活癖といってもよいもので、その代表が夜更かし朝寝坊です。夜更かしが癖になると睡眠不足で体調が悪くなります。
解消するにはつとめて体を動かすこと、適度な疲労は熟眠をうながし早寝の習慣をもたらします。
食べ物の癖とは好き嫌いです。かたよった食事を続けることは生活習慣病につながります。
そして、最も重要なことは、心の癖を直すことです。これまでの自分の人生を振り返り、自己中心的な行動がなかったかを反省し、もしあったら今後は改めること、そして感謝の思いを深めることが必要です。
自分自身を冷静に見つめ、悪いと思われる癖を見つけたら勇気をもって治しましょう。
悪い癖が1つ消えたらその分だけ、健康と幸せが近づきます。
参考文献 倫理研究所 「職場の教養」
投稿者: 井島鍼灸院
 手軽に健康法が楽しめるウォーキング。休日の朝夕は、全国の至る所でウォーキング姿が見られます。
手軽に健康法が楽しめるウォーキング。休日の朝夕は、全国の至る所でウォーキング姿が見られます。



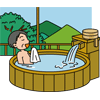 8月14日(火)に、初めて岐阜県揖斐郡揖斐川町にある「いび川温泉 藤橋の湯」に行ってきました。
8月14日(火)に、初めて岐阜県揖斐郡揖斐川町にある「いび川温泉 藤橋の湯」に行ってきました。 仕事の量、質に加えスピードも大きくアップ、さらにまったく新しい業務への対応も迫られる現代。
仕事の量、質に加えスピードも大きくアップ、さらにまったく新しい業務への対応も迫られる現代。 長谷川病院院長の柏瀬宏隆先生がストレスに負けない6か条を提言されています。
長谷川病院院長の柏瀬宏隆先生がストレスに負けない6か条を提言されています。 「ほめる人より叱る人」とはよく耳にする言葉です。人は誰でもほめられれば嬉しいものです。
「ほめる人より叱る人」とはよく耳にする言葉です。人は誰でもほめられれば嬉しいものです。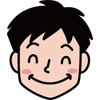 毎日を明るく朗らかな心で暮らすことの大切さは、みんなが知っていることですが、簡単には実行できません。
毎日を明るく朗らかな心で暮らすことの大切さは、みんなが知っていることですが、簡単には実行できません。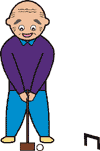
 昔から「病気治しは癖直し」といわれるように、病気には身体の癖、食べ物の癖、心の癖の3つが深くかかわっています。
昔から「病気治しは癖直し」といわれるように、病気には身体の癖、食べ物の癖、心の癖の3つが深くかかわっています。










